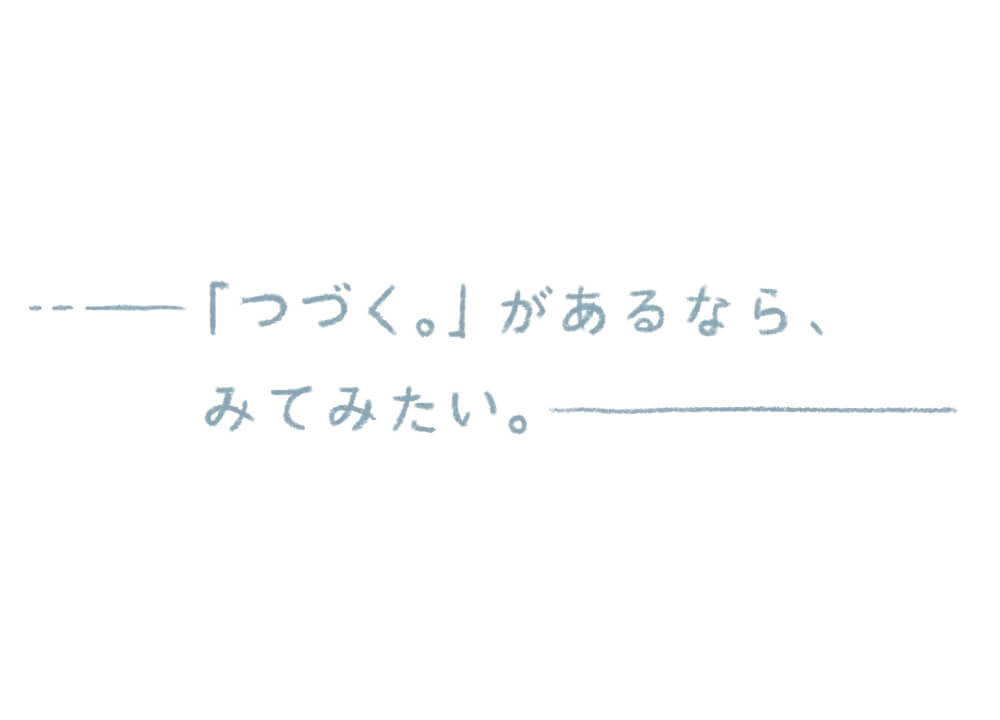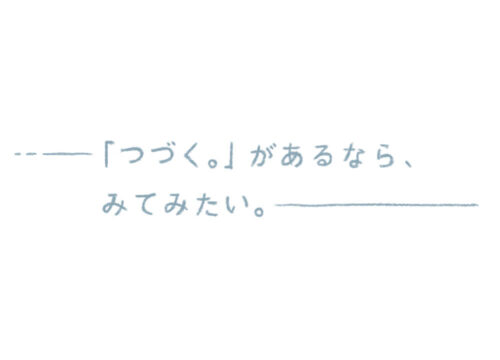「多忙」は、つづきのない、終わりへの一歩だ。
自分の暮らしを省みる中で、最近、特にそう思う。
普段から僕は「対話が必要だ」、「丁寧なコミュニケーションを心がけたい」、そう公の場で語ってきた。様々な社会問題の現場を訪ね歩く中で、孤独や孤立、誤解や偏見は、人々の心を追い込み、やがて寂しい結果を導き出してしまう。
「他者へ語りかける前に、自分自身との対話を重ねる時間を大切にすべきだ」、そうメディアに出て語ることも少なくない。
僕は本当は今どうしたいのか。
自分で自分の心の声に耳を傾けてあげないと、誰かがわかってくれるに違いないと思いながらも、救われなかったときに、その寂しさから身を守れないからだ。
でも、こうした言葉を口にするたびに、僕には後ろめたさがあった。なぜなら、今、自分にとって対話の時間が一番必要であることはわかり切っているのに、忙しさを理由に、目をそらし続けてきたからだ。
心の内側を自分で覗き込むにはあまりに厄介で、解の見えない自問自答の深淵にわざわざ自ら身を投げこむ余力が残っていない。
いつか壊れるんだろうな。
薄々そう感じているだけに、その漠然とした不安な気持ちの穴埋めを、他者の困りごとに関わり、救援側に守ることで、麻痺させてきた感は否めない。
他者への支援によって得る相手からの感謝は、一時の苦痛を和らげる。まるで麻薬のようなものだとさえ感じる。だから僕はしんどい時ほど、困りごとを見つけ出しては、彼らの一助になりたいと身を差し出してきたのかもしれない。
おそらく、そうした社会との関わり方に、つづく。はない。
そう思わせてくれるようになったのは、僕のマネージャーの一言がきっかけだ。
彼女は昨年から、僕の現場で様々なサポートを続けてきてくれた事務所のスタッフの一人だ。
一般企業からメディアの現場に転職してきた。
20代半ば。未経験な現場で不慣れな作業が続くものの「人を支えるのが好きだからこの仕事に興味があった」と語る彼女は、率先して「自分ができることがあればやります」と申し出てテキパキと動いてくれていた。
時間が経つにつれて、彼女の中でもさらにみてみたい未来が増えたのか、蔦屋書店で買ってきたという大判の書籍を鞄に詰め込み、デザインや撮影の勉強をしたりするようになった。
「実は、学生の頃から国際支援にも関心があったんです」と、いつの間にか社会起業家たちの言葉に熱心に耳を傾け前のめりな姿勢になっていた。そうした彼女の活動に僕も刺激を受けるようになり、何か自分が役に立てることがあればと協力を申し出た。
作業と作業のふとした合間の休憩時間。外の空気を吸いたいと思って出た事務所のバルコニー。「忙しいですけど、大丈夫ですか?」と気遣いの言葉と共に隣に座った彼女に、日頃の感謝と共にこんな言葉を投げかけてみた。
「俺は周りで働くみんなが、生き生きと、幸せそうに夢をかなえる姿を見るのをみてみたいし、応援したいんだよね。それが今の願いかも。」
僕の言葉を聞いた彼女はこういった。
「わたしは、わたしで自分のことを願えるので、堀さんは、堀さんの幸せを自分のために願ってください」。
気づきの多い言葉だった。
深呼吸をして、空を見上げた。
休んでみようかな。恐ることなく。
心の渇きに、水をやる時間をつくってみよう。ありがとう。